スリランカ研修報告(前半)
11月17日(日)から11月26日(火)までの10日間、スリランカを訪れ、現地の方々と交流を深めながら、紅茶の仕入れや茶園の視察を行いました。
今回の旅では、低地(ロウグロウン)から高地(ハイグロウン)まで、合計8つの茶園を巡り、さらに紅茶の研究所や製茶工場も見学しました。
茶園や工場へ向かう道のりは舗装されていない道が多く、トイレもなかなか見つかりません。首都コロンボを早朝に出発し、ガタガタと横にも縦にも揺れる車に揺られ、4〜5時間かけて茶園へ向かう旅路は、とても過酷なものでした。
しかし茶園や茶工場への訪問は、その疲れも吹き飛ぶほど勉強になり刺激的な体験でした。


茶園の工場に一歩足を踏み入れた瞬間、ゴーッという機械音が工場内に響き渡り、蒸された茶葉の青々とした力強い香りに包まれます。一部の茶園では撮影が禁止されているため、 スタッフ全員でこの機会を逃すまいと、目に焼き付けるように真剣に見学しました。
紅茶の製法は、季節や気温、天気、そして収穫後の茶葉の状態を見極めながら、各茶園のマネージャーによって絶妙に調整されています。特に、茶葉に含まれる水分量は、仕上がりの風味に大きく影響するため、湿気が多い雨の日には、茶葉を萎れさせる際に機械から出る風の温度を上げて水分を飛ばすなど、日々細かな調整が求められます。
マネージャーたちの術が紅茶の品質を大きく左右することを改めて実感し、紅茶は本当に繊細で奥深いと感じました!
 また、工場によって出来上がる茶葉のサイズも異なります。紅茶の製造工程には、石臼のような機械で茶葉をすりつぶす「揉捻」、そして大きさを選別する「等級分け」という作業があります。
また、工場によって出来上がる茶葉のサイズも異なります。紅茶の製造工程には、石臼のような機械で茶葉をすりつぶす「揉捻」、そして大きさを選別する「等級分け」という作業があります。
揉捻の回数によって、最終的に仕上がる茶葉のサイズは異なります。お茶の風味は栽培地域の環境だけでなく茶葉のサイズによっても大きく変わるため、市場の需要や最も美味しいとされるサイズを考慮しながら、マネージャーが適切に判断することが重要になります。
その後、様々なサイズが混ざった茶葉を等級分けし、カラーセパレーターと呼ばれる機械で色や形を識別して、枝や繊維などの異物を取り除きます。
茶葉のサイズを均一に整えることで、抽出時の味や香りが均一になり、風味が安定します。また、見た目の美しい茶葉はオークションで高値がつくため、作り手にとっても重要な工程です。


今回、地域の異なる8つの茶園で、私たちの紅茶が作られる工程を実際に目の当たりにし、人々の熟練の技術に触れたことで、得られた学びや経験はかけがえのないものとなりました。
休むことなく短期間で多くの茶園を巡ったため、決して楽な旅ではありませんでした。しかし、茶園の風景に囲まれ、工場の音や茶葉の香りを感じながら、茶園のマネージャーやスリランカのティーメーカーと情報を交換し、より美味しい紅茶を作るための議論ができたことは、非常に貴重な時間となりました。

また、最終日には、提携しているスリランカのティーカンパニーと、日本市場の現状や課題を共有し、改善策について話し合いました。共に紅茶産業を盛り上げることを誓ったミーティングは白熱し、気がつけば6時間以上が経過していました。
私たちはこの21年間、「美味しい紅茶」を追求することに情熱を注いできました。その姿勢はスリランカのティーカンパニーの人々にも深く響いたようで、多くの質問が寄せられ、私たちの取り組みに強い関心を持ってもらうことができました。
今回の研修を通じて、「美味しさ」に妥協せず挑戦を続けてきた信念が間違っていなかったことを改めて実感し、大きな励みとなりました。
これからも、美味しい紅茶を追求し、スリランカのパートナーと共にさらなる進化を続けていきます。
 ギフト
ギフト はじめての方へ
はじめての方へ ブラックティー
ブラックティー フレーバーティー
フレーバーティー ミルクティー
ミルクティー ハーブティー
ハーブティー ジュエルティー
ジュエルティー インフューズティー
インフューズティー 水出し紅茶
水出し紅茶 アウトレット
アウトレット スパイスカレー
スパイスカレー グッズ
グッズ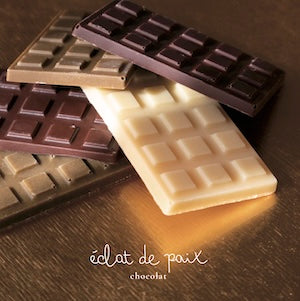 éclat de paix
éclat de paix